
企業の不正・不祥事、情報漏洩等の問題が後を絶たない状況であり、内部監査の重要性は増しております。また、企業におけるグローバル展開や内部統制実施基準の改訂等に伴い、内部監査・J-SOX評価の対象範囲は増える傾向にあります。一方、多くの企業においては、内部監査部門の人員は限られており、リソースが不足している状況です。リソースが限られていることを理由に、3年に1回のローテーションで各拠点の監査を行っているということも見受けられますが、各拠点のリスクが増えている中、内部監査の対応としては、不十分と考えられます。
そういったローテーションを埋めるための方法として、Webツールを活用した内部監査・内部統制対応があります。Webツールを活用することにより、訪問やヒアリングの負荷を軽減し、効率的な監査対応が可能となります。
今回の記事では、Webツール監査の特長・活用方法について、事例を交えながら、解説していきます。
Webツール監査の概要と特長
まずは、Webツール監査の概要と特長を説明していきます。Webツール監査とは、ITツールを活用した書面監査です。Web上のアンケートツールを介し、質問事項の確認・回答や証憑の授受等を行うものになります。Webツール監査であれば、各拠点に訪問し、ヒアリングを行わなくても、状況を把握することができます。また、拠点に対するモニタリング機能(牽制効果)を強化する手法になります。監査におけるローテーションの隙間を埋め、監査の時間と費用を節約できます。遠隔地に拠点を持つ企業様や多くの拠点がある企業様において、Webツール監査の効果は発揮されます。
Webツールの活用により、入力作業の軽減と迅速な回答・データ集計ができることも特長です。Excel等でアンケートを配布・集計することもできますが、Excelの場合、配布・回収、拠点側の入力作業、集計に手間がかかります。Webツール監査の場合、Webブラウザ上で回答を入力できるとともに、回答データは自動で蓄積されるため、集計の手間を削減できます。
Webツール監査を導入する際は、以下の手順で進めていきます。
①質問票の作成:現行の監査チェックリスト等に基づいて、監査項目を検討し、質問票を作成
②Webツールの設定:作成した質問票をWebツール上に登録
③質問票の配付・回収:各拠点に回答先を連絡し、質問票(Webブラウザ)の回答を依頼
④質問票の集計:各拠点にて回答した質問票を取り纏め、管理や統制状況の回答結果を集計
Webツール監査は、現地への訪問に係る時間や費用、ヒアリングに係る手間をかけることなく、現地の状況を効率的に把握できることが特長です。
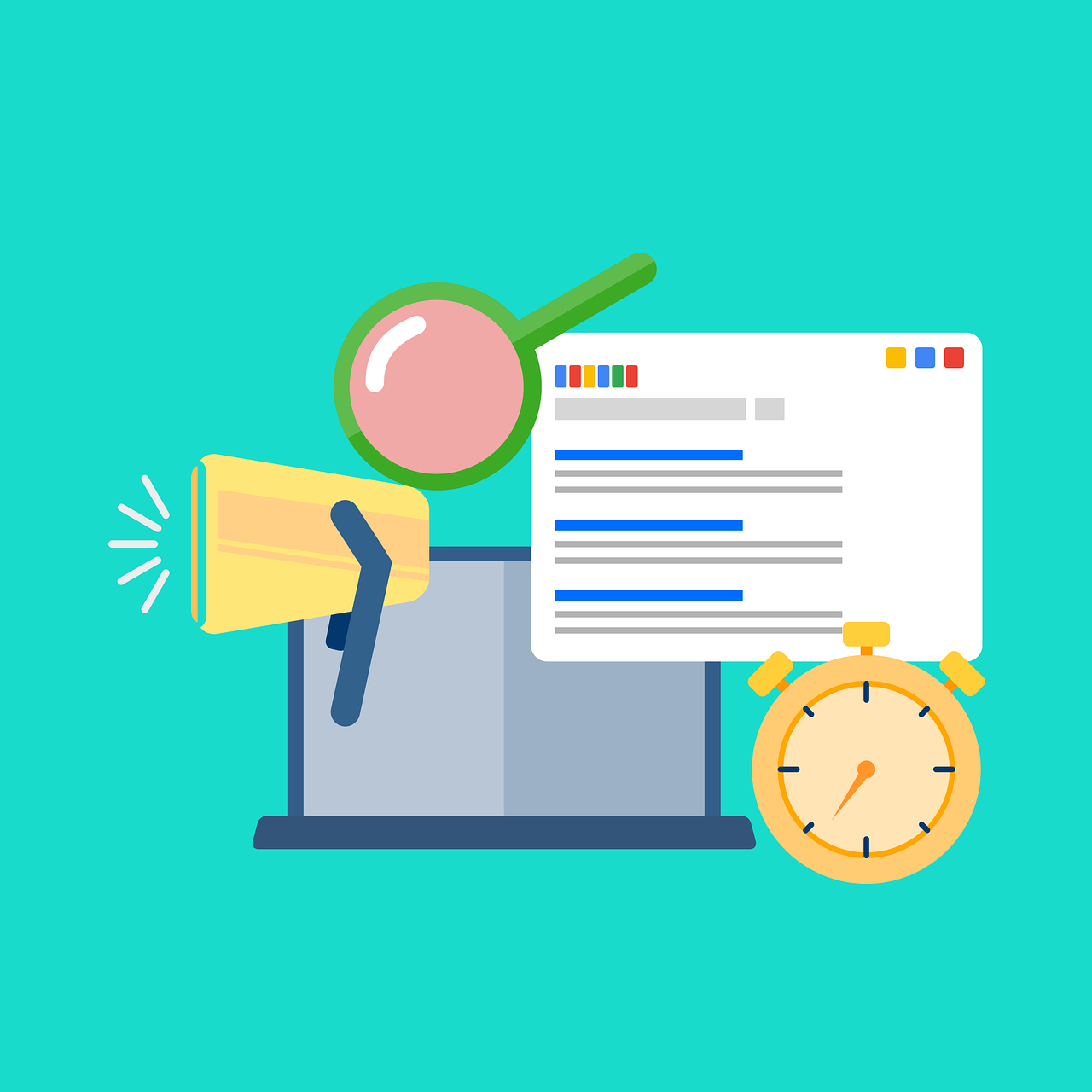
Webツール監査活用事例~内部監査~
次に、Webツール監査の活用事例をいくつか紹介していきます。まずは、Webツール監査を活用した内部監査の事例を紹介します。こちらは、国内・海外合わせて50社程度の子会社がある企業様の事例です。多くの子会社がある一方、内部監査部門のリソースが限られており、子会社の内部監査が実施できていない状況でした。不備・不祥事の発生を懸念し、各子会社の統制状況を確認するため、Webツールを活用して内部監査を行うことになりました。
Webツール監査の導入は、以下のように進めました。
①質問票の作成:現行の監査チェックリストを基に質問票を作成しました。その際、書面監査であることを踏まえ、優先度の高い監査項目に限定しています。また、質問文の見直し・更新を行っています。
②質問票の設定:作成した質問票をWeb上に設定し、各子会社に回答の依頼を行いました。海外拠点を含め、Web上に回答サイトにアクセスできるかの確認も行います。
③回答の集計:各子会社の回答結果を集計し、統制状況の分析を行いました。
これまで、内部監査が実施できていない子会社が多くあり、経営層・監査役等からも、指摘を受けておりました。Webツール監査により、監査のローテーションを埋め、監査実績を作ることができました。また、子会社別・監査項目別の集計結果から、統制が弱い子会社・監査項目を抽出し、次年度の監査テーマを検討材料にすることもできました。
質問票を作成するにあたっては、子会社側における回答の負荷を考慮することも検討ポイントです。対面ではなく、書面監査ということを踏まえ、監査項目の重要度・優先度を踏まえ、質問票を作成することがポイントです。
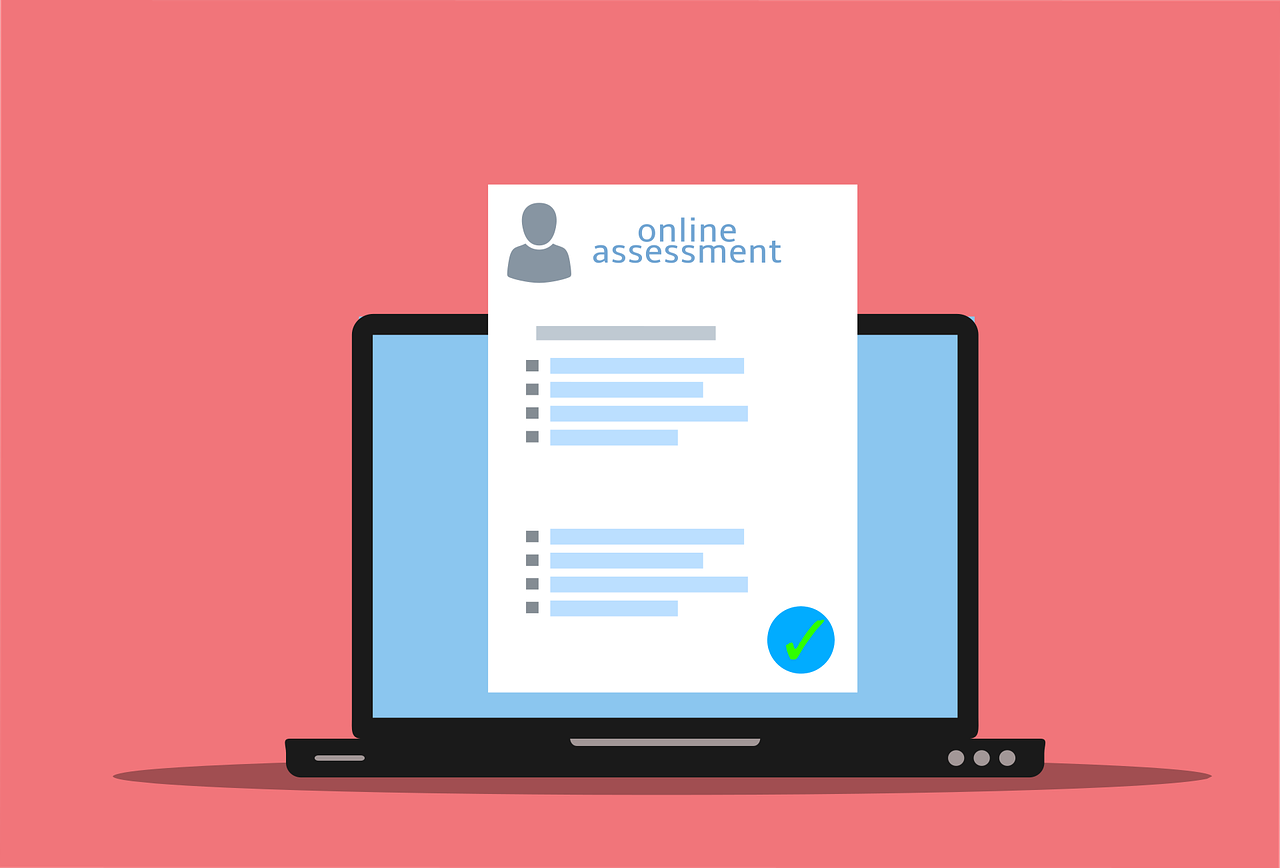
Webツール監査活用事例~内部統制構築~
次に、Webツール監査を活用した内部統制の構築事例を紹介します。この企業様では、内部統制実施基準の改訂に伴う評価範囲の増加が見込まれ、約30社の海外子会社を対象に、統制状況を把握するため、Webツールを活用した内部統制対応を進めることになりました。
Webツール監査の導入は、以下のように進めました。
①質問票の作成:現行の全社統制評価チェックリストを基に質問票を作成しました。「整備状況」「運用状況」の観点から、回答の選択肢を設け、質問票を作成しています。
②質問票の設定:Web上に質問票を設定し、回答の依頼を行いました。その際、合わせて、回答の根拠となる規程・証憑の提出も依頼しています。
③回答の集計:回答結果から、統制状況の確認を行いました。「整備状況」「運用状況」ともに未対応となっている拠点・評価項目を集計しました。
内部統制の「整備」「運用」の対応状況から、リスクが高いと考えられる子会社を把握できました。集計内容を子会社における質的重要性の分析結果として、J-SOX評価範囲の検討にも活用しています。本来、状況を把握するためには。現状を詳細にヒアリングすることが必要になりますが、Webツール監査を活用することにより、ヒアリング工数を削減できました。
J-SOXの評価と同様に、「整備状況」「運用状況」の視点から統制状況を確認することがポイントです。質問票の回答だけでは信憑性に欠けるということであれば、回答の根拠となる資料(規程・証憑)の提出まで求めることも有用です。
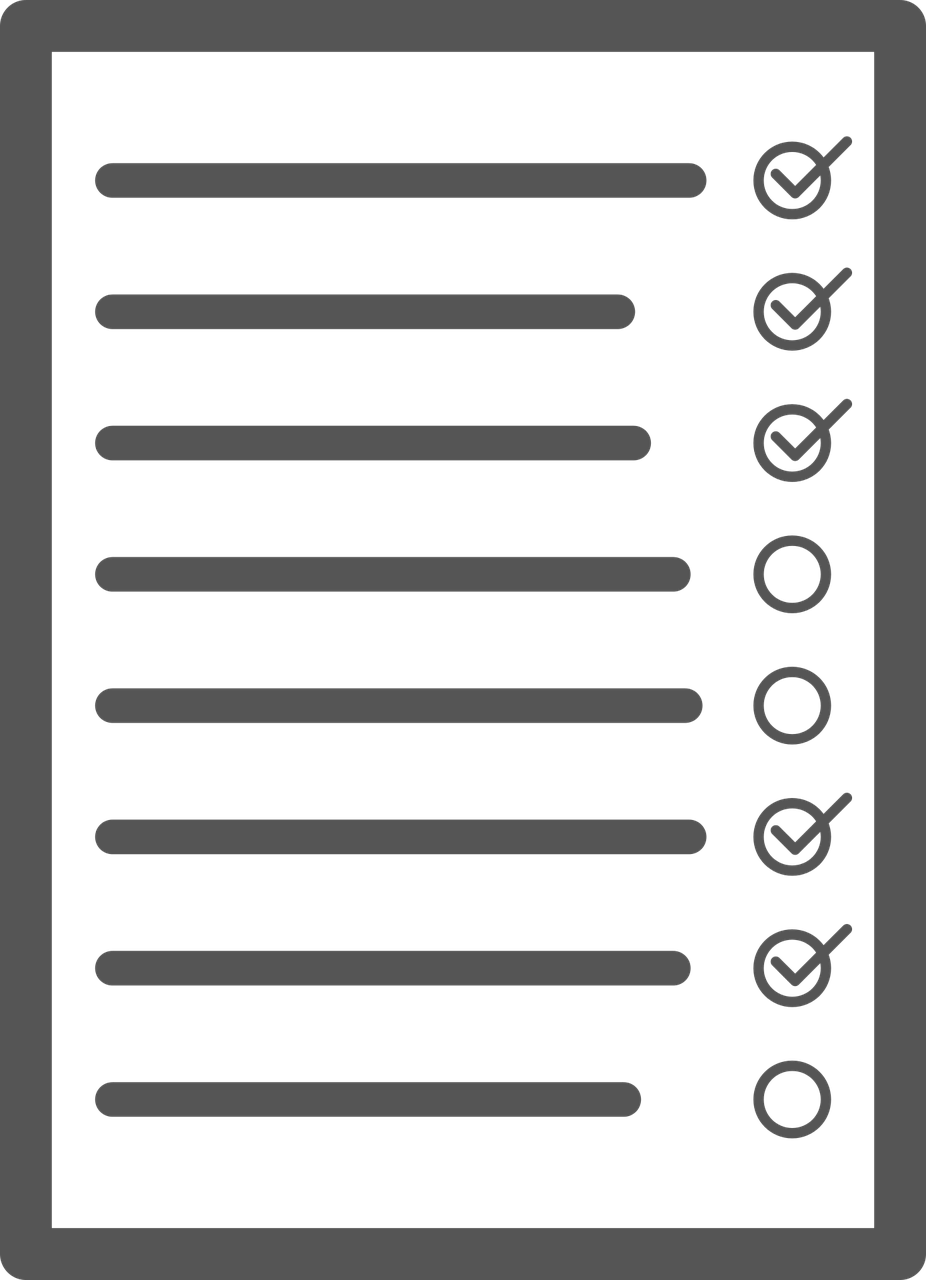
Webツール監査活用事例~内部統制評価~
続いて、Webツール監査を活用した内部統制評価の事例を紹介します。この企業様では、国内・海外合わせて、約20社が評価対象になっておりました。内部監査部門2名で、内部統制評価・内部監査を担当しており、リソース不足が慢性化していました。リソース不足を解消するための手段として、Webツールを活用して内部統制評価を行うことになりました。
Webツール監査の導入は、以下のように進めました。
①評価チェックリストの設定:Webツール上に、全社統制評価チェックリストを設定し、証憑欄を参照してもらい、証憑の収集依頼を行いました。
②証憑の収集:全社統制評価チェックリストを参照しながら、証憑を収集し、Webツール上に証憑を格納してもらいました。
③証憑の確認:証憑を確認し、評価調書の作成を行いました。証憑の不明点がある場合は、Webツールを介し、質問・回答のやり取りを行っております。
これまでは、評価対象の子会社が多く、証憑の依頼・不明点の確認等、子会社担当者との折衝に負荷がかかっていました。Webツールを活用することで個別に連絡を行うことなく、一斉に通知ができ、手間を省くことができました。また、Web上に証憑を保存することで、証憑の一元管理も可能となりました。
内部統制評価において、証憑の依頼・不明点の確認等、被監査部門とやり取りすることが多くあります。対象会社が多くなれば、連絡だけでも一定の工数がかかります。Webツール監査は、被監査部門との折衝を円滑に進めるための手段となります。

Webツール監査活用における留意点
最後に、Webツール監査の活用における留意点を説明します。Webツール監査では、ヒアリングの負荷軽減等のメリットがありますが、デメリットも存在します。メリット・デメリットを踏まえ、Webツール監査を検討する必要があります。Webツールの活用における留意点としては、以下のような事項があります。
・Webツール監査と往査の併用
監査テーマや各拠点の物理的距離・統制状況を考慮し、往査とWebツール監査を併用して内部監査を進めていくべきです。内部監査部門のリソース、監査対象拠点のリスク状況を踏まえながら、Webツール監査で確認できない監査内容があれば、往査で対応することも必要です。Webツール監査で対応するか、往査を行うかは、内部監査計画の策定時に検討します。
・実地状況の確認
Webツール監査では、施設内の状況確認は難しくなります。その場合、証憑として、写真や動画を撮影してもらい、検証する方法もあります。また、近隣拠点や監査対象以外の部門担当者に視察を依頼する方法も考えらます。実地状況の検証方法を検討し、Webツール監査で確認する監査項目を選別する必要があります。
・詳細状況のヒアリング
往査であれば、回答結果を踏まえ、追加で質問を行うことが可能ですが、Webツール監査では、詳細状況の確認は難しくなります。Webツール監査での回答結果では、理解できなかった事項等があれば、必要に応じ、個別でヒアリングを行うことも検討する必要があります。
今後、J-SOX評価の範囲拡大、監査テーマの増加等、内部監査部門の業務が増えることも想定されます。ツールを活用しながら、内部監査部門における業務の効率化・省力化を進めることも検討すべきです。
まとめ
■Webツール監査の概要と特長
☑Webツール監査とは、Web上のアンケートツールを介し、質問事項の確認・回答や証憑の授受等を行うものである
☑Webブラウザ上で回答を入力できるとともに、回答データは自動で蓄積されるため、集計の手間を削減できる
■Webツール監査活用事例~内部監査~
☑監査のローテーションを埋めることが可能である
☑子会社別・監査項目別の集計結果から、統制が弱い子会社・監査項目を抽出する
■Webツール監査活用事例~内部統制構築~
☑Webツール監査を活用することにより、ヒアリング工数を削減できる
☑内部統制の「整備」「運用」の対応状況から、リスクが高い子会社を把握する
■Webツール監査活用事例~内部統制評価~
☑一斉に通知ができ、担当者への連絡の手間を省ける
☑Web上に証憑を保存することで、証憑を一元管理することが可能である
■Webツール監査活用における留意点
☑施設内の状況確認は難しいため、写真や動画を撮影してもらい、検証する
☑理解できなかった回答等があれば、必要に応じ、個別でヒアリングを行う
